|
第五十一話 そしてAvantgardeを知り、組み合わせてみたいアンプ。 そんな贅沢な、しかも最初で最後になるかもしれないという垂涎のシステムでどんな世界が見えてくるのだろうか!? 9月28日のこと、展示期間をあと三日残すところとなったTRIO+6BASSHORNを惜しむように、やっと夢のペアリングが実現した。しかし、初日の音は到底納得の行くものではなかった。 恒例のPAD SYSTEM ENHANCERで徹夜のバーンインを繰り返し、TRIO+6BASSHORNが明日はなくなってしまうという最終日の30日に、とうとうその真価を発揮する演奏を聴くことが出来たのである。 その時のシステム構成は次のような組み合わせであり、マスタークロック・ジェネレーターのESOTERIC G-0sの加入がシステム全体をより高度な状態に仕上げてくれたようである。 ESOTERIC G-0s(AC DOMINUS) ⇒ Esoteric P-0s (AC/DC DOMINUS & RK-P0) ⇒ PAD DIGITAL DOMINUS AES/EBU 1.0m ×2 ⇒ dcs 974(AC DOMINUS) ⇒ PAD DIGITAL DOMINUS BNC 3ch/1tube(SPDIF-2) ⇒ dcs Elgar plus 1394(AC DOMINUS) ⇒ Viola BLUES SILVER INTERCONNECT 2m ⇒ Viola SPIRITO(AC DOMINUS) ⇒ Viola BLUES SILVER INTERCONNECT 6m ⇒ Viola BRAVO 2BOX SET (AC DOMINUS) ⇒ PAD DOMINUS SP BI-WIER 5m ⇒ Avantgarde TRIO+BASSHORN(With PAD TANTUS & MIZUNOSEI SPK) まず、最初に聴きなれたDavid Sanborn「TIMEAGAIN」をかけてみることにした。三日間という熟成の時間を経て、Violaを核とするシステム構成でTRIO+6BASSHORNはどのような変貌を遂げているのか期待の一瞬である。さあ、一曲目の「COMIN' HOME BABY」がスタートした。 「えっ!? これは違うぞ!!」 イントロで始まったスティーヴ・ガッドのブラシワークの鮮明さ、クリスチャン・マクブライドのベースの重量感、それらリズムセクションの緊張感に目を見張り解像度の高まりに思わず唸ってしまった。特にドラムヘッドに軽やかに打ち下ろされるブラシが、それ自体にしなりを加えてヒットする瞬間にブラシの先端の一本一本が明確に独立している様が感じられるのである。 そしてそのブラシのスピーディーで軽快なアクションにピンスポットが当てられたように、以前にも増して音像を目の前に差し出してくる躍動感として私の感性をヒットしてくるのである。これには驚いた!! そして、デヴィッド・サンボーンのアルト・サックスが入ってきたときに、その音像がこれまでにないほど凝縮されていることにわが耳を疑ってしまった。 シャープな音像表現に変化していくと、それ自身の質感が硬質化してしまい耳に刺さるような刺激成分を図らずも含んでしまう演奏を経験したことが多々あるが、 リードの質感を極めて微妙なヴァイブレーションとして発散し豊富な余韻感に周囲を包まれているので極めてストレスフリーな質感なのである。 マイク・マイニエリのヴァイブを前述では"漂うような…"という表現をしていたが、このときのヴァイブはヒットの瞬間が際立って鮮明になっているので、TRIOの両翼に展開する打音の連続は しっかりと空間にきらめきを見せるので明らかに前言撤回という印象だ。  とにかく、打楽器のインパクトがこれほど鮮明になろうとは予想もしていなかったので、それでは…、ということでドラムでの反応を見ることにした。
ドライな録音というか、極力演出をしていないレコーディングでドラムの質感をチェックするにはこのディスクが最適だ。
dmpのMorello StandardからTake Fiveを聴く。 とにかく、打楽器のインパクトがこれほど鮮明になろうとは予想もしていなかったので、それでは…、ということでドラムでの反応を見ることにした。
ドライな録音というか、極力演出をしていないレコーディングでドラムの質感をチェックするにはこのディスクが最適だ。
dmpのMorello StandardからTake Fiveを聴く。
「おー!! このスピード感は何なんだ!!」 このときのJoe Morelloは凄まじかった!! 今まで何年間もこの曲を聴いてきたのだが、これほどアタックが早い高速な立ち上がりのドラムは聴いたことがない。 他のシステムで聴いてきたドラムの音は、いうなれば太鼓に張りつめた皮というイメージがあり、打撃の瞬間ではスティックがはね返されるような 何がしかの弾力性をもったドラムヘッドをイメージしたものであった。しかし、このときの打音は違った。皿を硬い床に叩きつけたような"破砕音"のようでもあり、スネアーのテンションがパリンッ!! と音をたててTRIOの前面で炸裂するのである。そして、キックドラムの音。これがBASSHORNのチューニングがやはり正しかった、と再確認させてくれるように「ダッ、ダッ、ダッ!!」と乾いた波動を打ち出してくる。 「ドスッ、ドスッ、ドスッ」ではない、もっと高速なブレーキングによってイコランジングしていないキックドラムの質感がリアルサイズの打音を、高速にかつゆとりを持って再現している。 「いや〜、Avantgardeって、こんなに凄いドラムを鳴らすんだ!! 全然イメージが違うぞ!!」  という驚きにそそられて、もう一枚のJoe Morelloをかけてみる。 という驚きにそそられて、もう一枚のJoe Morelloをかけてみる。Going Placesからは、この一曲Autumn Leavesである。 この曲はドラムとウッドベースという珍しいデュオの演奏なのだが、そのスリリングなドラムはたちどころにスピーカーの性格を暴露してくれるものだろう。 さあ、この曲がスタートしたらCDプレーヤーのカウンターを見ていて欲しい。ブラシを使った小気味よいリズムとキック ドラムの正直な音がベースと絡まりあって展開していくその時、スタートしてからカウンターが00:24を示した瞬間に炸裂するスネアーの打音が私をのけぞらせたのである。 直接音を85%リスナーに伝えるというAvantgardeの理論とはこれのことなのか。そして、その瞬発力を寸分たがわず発揮されるViolaとの相乗効果なのか。 はたまたルビジウムによって楽音のにじみを究極的に取り払ってくれるG-0sの貢献なのか。とにかく、この一瞬のアタックの素晴らしさは筆舌に尽くしがたい爽快感を持って私を魅了してしまった。 そして、ドラムのエネルギッシュな演奏もさることながら、巨大なBASSHORNを背景にしてGary Mazzaroppiのベースがきっちりと輪郭を見せる解像度の高い演奏が、 BASSHORNのチューニングにおける節度を裏付けているではないか。これでいい!! 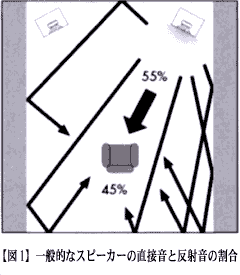 私は過去の随筆で音波の性質を「音の天気予報 その1」と「音の天気予報 その2」で、
そしてスピーカーのデザインの原理も「職人の千里<耳>眼」というタイトルで述べているので基礎知識として再読して頂ければありがたいものだ。
私は過去の随筆で音波の性質を「音の天気予報 その1」と「音の天気予報 その2」で、
そしてスピーカーのデザインの原理も「職人の千里<耳>眼」というタイトルで述べているので基礎知識として再読して頂ければありがたいものだ。そこでも触れているのだが、音圧は距離の二乗に反比例して減衰するという性質がある。 そして、音波は音源から360°のあらゆる方向に球面体で、毎秒340m/秒という等しい音速で進行・拡散していくという原理を思い出して頂けただろうか。 さて、その原理原則にのっとって図1をご覧頂ければと思う。これはAvantgardeの資料からの転記であるが、 長年Nautilusをリファレンスとしてきた私には彼らの言わんとしていることは大変に良く理解できるものだ。 これはNautilusが室内で発生する間接音を、このように多分に含んでいるから良くない…、という単純なものではない。 この図は直線音を効率よくリスナーに届けるという同社の考え方を優先して作られているものなので、スピーカーのデザインと音波の拡散パターンの重要性には触れていないことを私から補足させて頂く。  さて、ここでもう一つ注目しなければいけないのがAvantgardeの製品で大きな特徴とされる高能率である。
TRIOにおいては109dB/1w/1mという驚異的な高能率なのだが、スタジオユースを前提にして設計されたB&WのNautilus801の91dB/2.3V/1mと比較すると、
なんと実数値では約63倍という感度の違いが存在することになる。これをどのように理解するかが大切なのだが、B&WのN801よりも同じ出力で63倍の音量を出すことが出来る…、という事ではないのだ。
単純に高能率=大音量という発想はPAやSRのようなコンサートのための業務用スピーカー並に大きな音響出力が可能だ、
という事とはまったく逆の発想が家庭用スピーカーとしてのAvantgardeの設計思想の根幹なのである。
それは同じアンプの出力の中に潜む63分の1という微小信号を音として取り出すことが出来るということなのである。
能率が90dB程度かそれ以下というスピーカーが主流を占める近代のオーディオシーンの中にあって、それらよりも60倍以上の感度を持っているということは、
私達が聴き取ることの出来なかった極微小な情報を見事に引き出してくれるということは本当に意義深いものがあるということだ。最後にもう一つだめ押しの快挙。
BASSHORNの感度は99dB/2.83V/1mという事実である。 さて、ここでもう一つ注目しなければいけないのがAvantgardeの製品で大きな特徴とされる高能率である。
TRIOにおいては109dB/1w/1mという驚異的な高能率なのだが、スタジオユースを前提にして設計されたB&WのNautilus801の91dB/2.3V/1mと比較すると、
なんと実数値では約63倍という感度の違いが存在することになる。これをどのように理解するかが大切なのだが、B&WのN801よりも同じ出力で63倍の音量を出すことが出来る…、という事ではないのだ。
単純に高能率=大音量という発想はPAやSRのようなコンサートのための業務用スピーカー並に大きな音響出力が可能だ、
という事とはまったく逆の発想が家庭用スピーカーとしてのAvantgardeの設計思想の根幹なのである。
それは同じアンプの出力の中に潜む63分の1という微小信号を音として取り出すことが出来るということなのである。
能率が90dB程度かそれ以下というスピーカーが主流を占める近代のオーディオシーンの中にあって、それらよりも60倍以上の感度を持っているということは、
私達が聴き取ることの出来なかった極微小な情報を見事に引き出してくれるということは本当に意義深いものがあるということだ。最後にもう一つだめ押しの快挙。
BASSHORNの感度は99dB/2.83V/1mという事実である。このような背景を元に私が感じたドラムの鮮烈さを分析すると、正に上記に述べてきた事柄がAvantgardeの醍醐味として思い起こされるのである。 ここで図2をご覧頂きたい。TRIO+6BASSHORNで実現したとんでもない高能率が録音の奥底に眠っていたミクロの楽音、ニュアンス、空気感、それらを情報として鮮明に引き出したとしても、 リスナーに届く前の空気中でロスしてしまったのでは元もこうもない。しかし、これまでに述べてきたように、私が今まで皆様に推奨する気持ちを持ち得なかったホーンスピーカーという分野において、 納得できなかった要素をAvantgardeはSpherical hornという新技術、あるいは以前から原理は存在していたもののユーザーに手に出来る商品として提供してくれたことによって、 私の既成概念はことごとく覆されてしまったのである。それを象徴するのが直接音の85%をリスナーに届けるという自信たっぷりなAvantgardeが作成したイラストである。 Joe Morelloのドラムがそれほど素晴らしかったのはなぜか!? いや、それだけではなく他の多くの曲においてもバックバンドできちんと叩かれているパーカッションを、 これまで見過ごしていたということを明確に私に訴えてくるのである。持続する楽音はボリュームの上げ方で拡大することは出来るが、 ほんの一瞬で叩かれて消えていく打楽器には、演奏者の情熱をそれと感じさせてくれるスピーカーの登場に私は大きな拍手をおくりたいものだ!! さて、前述のように99dB/2.83V/1m という極めて高感度なBASSHORNのチューニングを考えると、さっとひらめいたのがこのディスクだった。  やはり今は廃盤になってしまったが、
Jennifer WarnesのThe Hunterである。
この8トラック目の「Way down deep」は、これまで数多くのスピーカーでバスレフポートから盛大にエアーを排出して、そのタブラを音源にしたサンプリングの低域における再現性のあり方を教えてくれたものだ。 やはり今は廃盤になってしまったが、
Jennifer WarnesのThe Hunterである。
この8トラック目の「Way down deep」は、これまで数多くのスピーカーでバスレフポートから盛大にエアーを排出して、そのタブラを音源にしたサンプリングの低域における再現性のあり方を教えてくれたものだ。さあ、ここではどのような暴れ方をするのだろうか? と意地悪な期待感をもってディスクをローディングした。 するとどうだろうか!? 連続する大振幅の低域音源によって、これまでのスピーカーではこの低域のコントロールにおいて散々苦労させられてきたものなのに、いとも簡単にBASSHORNはその重量感、スピード感、 テンションのあり方を私が体験したことのないレベルできっちりと再現するではないか!! しかも、その後に登場するジェニファーのヴォーカルが何とも見事に中空に定位し、低域のモーメントに影響されない解像度を見事に提示する。 2ウェイ、3ウェイのスピーカーで皆さんはこんな実験をしたことがあるだろうか? それらのスピーカーの入力端子がバイワイヤーであり、ウーファーのみに接続してヴォーカルの入った曲を再生してみるのである。 スペックでは100Hzから300Hz程度のクロスオーバー周波数で帯域分割していると言うのだが、それだったらヴォーカルの帯域のかなり下で区切られているはずだ。 しかし、大半のスピーカーではウーファーのみ接続すると、そこからヴォーカルが聴こえてくるのである。 さて、ここで私は最初にティアックの試聴室を訪れたときに、真っ先にやった実験を思い出した。TRIOの接続を解除してBASSHORNのみ鳴らしてみたのだ。 すると…、まあ何とも見事に完全に低域のみでヴォーカルは微塵もBASSHORNからは聴こえてこないのだ。当たり前だが実は中々このようなスピーカーはないものだ。 上記に私は"低域のモーメントに影響されない解像度"と述べているが、ウーファーの再生音を周波数の上の方向へ目を向けて考えると前例のようなヴォーカルを含む中高域の帯域を再生してしまうことで、 上の帯域に対する混変調の要因を含んでくるものである。 そして、一般的なウーファーの動作で今度は下の周波数の方向へ目を向けてみると、ウーファーの上限のクロスオーバー周波数の10分の1となる帯域もいっしょに再生するという事実である。 録音年代が古いものは、あまりその影響を受けないだろうが、近代の録音では上記のように100Hz以下を含むものは結構多く見受けられる。最もポピュラーでありながら、その録音成分を見逃しているのがこれ、 Eric Clapton「Un plugged」であろう。 この3、7トラックの冒頭に入っている低域は、Claptonがテレビ局のスタジオに設営された台座の中が空洞のステージを足で叩いてリズムを取る場面で聴けるものだが、 このようにウーファーの動作には10倍以上の違いがある周波数を、それも大振幅で再生しなければならないという宿命があり、前記の "低域のモーメントに影響される状況"というものを私は強く感じてしまうのである。つまり低域再生においても混変調歪は多分に発生しているということだ。 しかし、それはスピーカーのエンクロージャーの設計やバスレフポートのチューニングによる"ノリのいい気持ちいい低音"という演出にマスクされてしまって 中々その正体に気付かない人々が多いということなのだ。 周波数が低くなればなるほど一定の音圧を求めると振動板の振幅は必然的に大きくなってくる。 100Hz以下の超低域を出力せんがために、大きくストロークを繰り返すウーファーに数百Hzの音声が同時に再生されるということが、私が言いたい"低域のモーメント"なのである。 それがTRIO+6BASSHORNでは一切感じられないのである。 TRIOのLow-/Midrangeホーンは第二部の図4でわかるように100Hz以上を受け持っている。 しかも、それには他のスピーカーのようにエンクロージャーという"演出家"を一切否定した箱のない低域の再生を行っているものだ。 ちなみに、このシステムでBASSHORNの接続を外してしまうと、一般的な解釈での低音はほとんどなくなってしまう。 測定器では正確に100Hz以上のレスポンスを持っているのだろうが、肉眼…、いや"肉耳?"で聴いてみると箱の演出でサポートされない100Hzから600Hzの低音というのは驚くほど無いに等しいボリューム感なのである。 私から見ると、それは正攻法で周波数特性をにらんだ場合には極めて正確な低域再生ということに他ならない。 つまり、一般的なウーファーから100Hz以下の再生という重荷を取り去ってやると、本当に純粋でハイスピード・ハイテンションな低音が再現できるということなのである。 BASSHORNの貢献は大変に大きなものであるということだ。 そんなことを考えながら、更に意地悪なテストを…ということで、実測で28Hzが録音されているという10トラック目の「I can't hide」をかけてみることにした。 イントロからドラムロールが展開するが、たっぷりとイコライズしてリヴァーヴをかけてゆったりとした低域だが、その奥深さは尋常ではない。 そのうねりのような低域の波間からすっくと立ち上がったかのようにヴォーカルやパーカッションが空間に表れてくる。 そして、Avantgardeのスピーカーで聴くヴォーカルに共通することなのだが、まるで3D映画のようにリスナーの眼前に熱のこもったヴォーカルをステージがせり出して来たかのように、 “ほら、そこに…”と言わんばかりに距離感を縮めて提示するのである。 この温度感の高まりと解像度の素晴らしさは未体験のものであった。 ここでも、ヴォーカルを彩るバックとしてクラビスなどのパーカッションが「カチーンッ!!」と叩かれるのだが、 この一瞬の打音の保存性は何と素晴らしいことであろうか。そして、キックドラムの切れ味は正に低域のモーメントから開放されて小気味良く途切れ、 トライアングルの打音は輝きスチールギターの響きが濃厚に漂う。 私がこれまでに聴いてきたスピーカーよりも63倍の感度が、わずか15%の間接音という鮮度で届けられると音楽とはこれほどまでに変貌するのだろうか!? 演奏が熱いのだ!!  低域の大きな振幅が中高域にいかに影響をもたらしていたか、これを逆説的に具現化したのがTRIO+6BASSHORNであるということだ。 低域の大きな振幅が中高域にいかに影響をもたらしていたか、これを逆説的に具現化したのがTRIO+6BASSHORNであるということだ。そして、この辺まで聴き進んでくるとそれでは果たしてどのくらいの超低域における再生能力があるのか、このディスクを使って試してみたくなった。 鬼太鼓座の「伝説」の1曲目、ズバリそのもののタイトルで「大太鼓」である。 他の一部の和太鼓のディスクに収録されていた大太鼓の音が、演奏空間に残存する「ぶるる〜ん、ぶるる〜ん」 というインパクトの後に残る残響を誇張したような録音が見受けられる中で、ここでの大太鼓は正にインパクトの瞬間に目に見えて震える太鼓の皮の振幅を捉えている録音なのである。 そして、その大きな振幅にきちっと制動されなければ、このディスクの持ち味がわからないものだろう。 これまでにも多数のスピーカーで聴いてきたが、各々のキャビネット構成とウーファーの特質から、録音されていない低音がいかに演出を加えているかということをわからせてくれたものだ。 さあ、冒頭は尺八の独奏から始まる。時折聴こえてくる金物のリズムに尺八の息遣いが交じり合って、刺激のない、それでいて鋭い尺八のイントロが続く。そして、最初の一打!! それまでBASSHORNの巨大さに畏怖の念を持ち固唾を飲んで、どれほど"おどろおどろした大太鼓"が飛び出してくるのか、という怖いもの見たさの期待感とも言える心境が聴く人の胸に宿るものだ。 この音圧にしてインパクトの鋭い大太鼓が打ち鳴らされた瞬間に、その予想は大きく覆される。 エンクロージャーという決められた容積を持つスピーカーが、 ウーファーの振幅が目に見えるほどにストロークしている、いわば高速で回転させないとトルクが得られないエンジンのように必死に超低域をひねり出しているという印象はさらさらないのだ。 BASSHORNのドライブにも前出のように最新のサーボテクノロジーが使われているものの、ホーンロードをかけられながら正確なブレーキングがきちっとかけられ、 その大太鼓は重量感をたたえながら軽く反応しインパクトの瞬間が鮮明に描かれるのである。 確かに部屋の空気を揺さぶるのだが、それはぴたっと挙動と静止とを繰り返し、 私がこれまでに体験したことのない透明度の高い演奏空間を見せてくれるのである。 前述のように100Hz以下の再現性をBASSHORNがどのように確保しているか、そのBASSHORN自体が再生する帯域に関係してくるのが独自のテクノロジーADRICである。 この大太鼓の響きを従来のスピーカーでの体験と比較しながら、私は6台のBASSHORNが使用される場合ADRIC回路は、24Hz以下を補償するというコメントをしみじみと思い出してしまった。 これまでのスピーカーでは、この大太鼓の打撃から残響の終息まで、今思い出してみるとうねりのような脈動感というか、ウーファーとエンクロージャーの演出によるエネルギー感の変動があったようなのだ。 しかし、それも低音の演出という欺瞞を心地良いと錯覚しながら聴いてきたということが、たった今わかってしまったようなのだ。素晴らしい!! 私が理想とする箱のないスピーカーとは正にこのことだ!!  さて、これまでは打楽器を中心にして、打ち出される低域に関してBASSHORNの素晴らしさを聴いてきたが、通奏楽音としての低域の表現力はどうだろうか? と、
これまた廃盤になってしまった古いディスクを取り出してきた。
さて、これまでは打楽器を中心にして、打ち出される低域に関してBASSHORNの素晴らしさを聴いてきたが、通奏楽音としての低域の表現力はどうだろうか? と、
これまた廃盤になってしまった古いディスクを取り出してきた。あのWilson Audioの「Discovery and Music for Christmas」である。1989年の作品であり、ご紹介できるジャケットの画像もないのだが、Dr. James Welchによるパイプオルガンのソロである。 これも色々なスピーカーでパスレフポートから盛大にエアーがあふれ出てきて、楽音の輪郭を表現するのにやっかいなディスクである。 そして、オルガンの極低い特定の音階になると、その鍵盤を指が押した瞬間にポートとキャビネットの低域共振によって、その一音だけが音圧がぐっと盛り強調されてしまうというやっかいな録音だ。 さあ、始まった…。 まず冒頭の数秒間を聴いて直ちに感じられることは、先ほどの鬼太鼓座での尺八でもそうだったのだが、オルガンのリードとしてスリットを空けた金属管に空気が吹き込まれ、 そのヴァイブレーションがTRIOとViolaの貢献によってか素晴らしく鮮明に聴き取れることである。 かすれたような響きを何のストレスもなく吐き出すオルガンに、まずこれまで聴こえなかった情報量の大きさを直感した。 パイプオルガンの低域は部屋全体を包み込むような豊満な響きをするものだが、それに対して同じ楽器が発する中高域の“管の共鳴音”は見上げるような高さと距離感を印象付けるものだ。 リードと空気の摩擦感というのか、そのかすれながらの発音が85%の直接音による情報としてTRIOの周囲を駆け巡るとなんともリアルであることか!! 楽音のエネルギーを保存する…、いや再現するということがいかに感動的であるか、この冒頭部分の演奏で私の耳を釘付けにしてしまったのである。 そして、次第に低い音階に向けて演奏者の指が運ばれていくと…、今まで、その一音で唸りを交えたかのように音圧が高まっていたパートがあっさりとこなされていくではないか!! 超低域の連続で素肌に音があたって産毛が、ささっと揺さぶられるような感触を感じているのだが、従来のように皮膚に微妙な圧迫感を与えるような低域ではないのだ。  オルガンの低音階では正確な脈動感がきちっと再現され、その脈動の一山一山がどんなに音階が下がっていても見事に再現される超低域のトランジェントは過去の記憶に照合してもなかったものだ。
オルガンの低音階では正確な脈動感がきちっと再現され、その脈動の一山一山がどんなに音階が下がっていても見事に再現される超低域のトランジェントは過去の記憶に照合してもなかったものだ。低域のモーメント現象はここでもしっかりと確認できた。低域のエネルギーを蓄積しては放出するという音響的コンデンサーのような、エンクロージャーによる低域の演出から開放されると何と素晴らしいことか。 ついついBASSHORNの素晴らしさに耳を奪われがちだが、今回このオーケストラを聴いて今までにない爽快な印象を持ったものがある。 エサ=ペッカ・サロネン指揮によるロスアンジェルス・フィルハーモニックのGUSTAV MAHLER 交響曲第3番ニ短調である。 その第一楽章のホルンを中心とした管楽器の表現力において、600Hzから4KHzを受け持つミッドレンジとトゥイーターを擁するTRIOの中高域の連続性の素晴らしさにしばらくはうっとりと聴き入ってしまった。 今まで他のスピーカーで聴いた時には感じられなかった管楽器の響きの美しさが、前述のヴォーカルでの印象と同様に濃厚に、そして抜群の切れ味で引き立てられていく。 ロス・フィルにしては遠めに聴こえていたそれらが、これほどの色彩感を伴ってTRIOの身の丈そのものの上方からゆったりとホルンが響き渡る快感は、今まで他のスピーカーでは感じられなかったことである。 そして、この主題がヴァイオリンのソロで中央やや左よりから演奏されたとき、TRIOのミッドレンジから4KHz以上を引き継ぐトゥイーターへの連続性が極めて自然なことに思わずため息をつく。 最初にCDCシステムという耳慣れない単語を聞いた時には一体何のことかわからなかったが、これまで解説してきたようにクロスオーバー・ネットワークによる電気的な帯域分割に依存しない新しい手法は、 ホーンシステムという古典的なアイテムを使用する上で間違いなく音質に貢献する近代化を成し遂げているのであった。 思えば通常のスピーカーよりも63倍という感度を持っているということは、再生音に含まれる歪成分にも敏感になるということだろう。 それは私だけでなく、ここを訪れたユーザーにも面白いエピソードを残していった。 ある曲のソプラノのヴォーカルがフォルテになると声が歪むという現象を確認したのである。今までそんなことはなかったのだが…!? それは、Avantgardeでは感じることが出来たのだが、他のスピーカーではわからなかった。 実はこの時にはdcs Elgar plus 1394→HALCRO dm8という組み合わせで、音質的に評価しているElgar plus1394の出力を6Vのハイレベルで使用していたのである。 それまで色々と配線を変えて、この歪感の原因がどこにあるのかと調べていくと、HALCRO dm8から他のプリアンプに切替えると症状がなくなるのである。 「お〜、原因はここか!? 」 と輸入元のサービスで調べてもらったがHALCROに異常は認められなかった。そして、HALCRO dm8は通常のCDプレーヤーの出力が最大変調時では2Vの定格出力ということで、これに合わせて入力段を設定しているということが判明した。 つまりは、Elgar plus1394の6V出力がHALCRO dm8のライン入力の許容範囲をオーバーしていたということが原因であったのだ。 両者ともに異常なしであり、偶発的にセッティングした組み合わせの設定に問題があったのだ。 これを突き止めるまでにAvantgardeも疑ってティアックにも検証して頂くなど、各社にお手数をおかけしてしまったのだが、他のスピーカーでは感じられなかった微妙な歪感を見事に検出するAvantgardeは、 言い換えれば楽音をそれだけ正確に再生するということだ。 繰り返すが直接音85%、そして他社のスピーカーに比較して63倍の感度。これが皆様の部屋にセッティングされた暁には、これまで見えなかった世界が現れること請け合いである。
このセッティングではSUB230CTRLがTRIOの陰になって前方からは見えないと言う絶妙な位置関係によって一般家庭で使用されているという好例と言えるのでご紹介しておく。 更に、AvantgardeではBASSHORNを二台単位でTRIOのセンターに置けない場合には、BASSHORNを垂直に立てることによって大分スペースセービングになること。また、BASSHORNを二台別々に部屋のコーナーに設置することなども推奨している。しかし、そうは言ってもまだまだ巨体であることに変わりはないだろう。前頁の大間知 邸頁ではSUB230CTRLが大変納まりよくセッティングされているのだが、このSUB230CTRLでさえもコンパクトながら大変な能力を持ったサブ・ウーファーなのである。それを承知していながらAvantgardeはなぜBASSHORNのような怪物を作り上げたのだろうか? BASSHORNにはあってSUB230CTRLにはないものがあるのだろうか? これを問い合わせたところ次のような回答があった。
つまり、超低域の振幅の大きい信号と、それ以上のものを完璧に分離してやることで、すべての帯域で楽音の鮮度が向上するということだと考えられる。 また、これは余談であるがHolgar Fromme氏が数年前にBASSHORNのアイデアと開発を社内で発表したときには大変な猛反対があったそうだ。 それを押し切って独断で開発を進め、先ずは自分で買い取るから自分の自宅に1セットをセッティングしろ!! ということで自室にセッティングされたTRIO+6BASSHORNを写真29で紹介したものだった。 そのBASSHORNを発表・発売してから、まだ一年も経っていないのに同社が生産し出荷した台数は何と!! 200台に及ぶBASSHORNを世界中に送り出しているというから驚きではないか!? さて、一音一音を、そのディティールをひたすら鮮明に表現していくAvantgarde は録音の錬度をつぶさに聴き手に伝えてくる。 スタジオモニターとしては実用的ではないかもしれないが、その解像度の素晴らしさと間接音の影響を受けにくい体質という見地から、ユーザーが評価しうるディスクに厳密なレベルの格差を認識させてくれる。 そして、同時にViolaというアンプがニュートラル性を追求しているという姿勢が、これほど敏感なAvantgardeというパートナーを得たときに、それ自身のクォリティーを立証する格好の機会となってくれた。 実は、その余波はここH.A.L.での体験だけではなく、当社の第27回「マラソン試聴会」においても同じペアリングがイベントのフィナーレを飾ることになったのである。  その模様は私のBrief Newsでも公開しているが、ここで演奏された音楽の実体験によって更にBASSHORNがなぜ必要になったかという前述のポイントが、
今回の会場となった大きな空間での実演によって証明されたものであった。
鬼太鼓座の「伝説」の1トラック「大太鼓」の演奏は、この画像のスピーカー位置から10メートル以上離れた客席の皆様に大きなインパクトを与えたものだった。
その模様は私のBrief Newsでも公開しているが、ここで演奏された音楽の実体験によって更にBASSHORNがなぜ必要になったかという前述のポイントが、
今回の会場となった大きな空間での実演によって証明されたものであった。
鬼太鼓座の「伝説」の1トラック「大太鼓」の演奏は、この画像のスピーカー位置から10メートル以上離れた客席の皆様に大きなインパクトを与えたものだった。自分と試聴室から、この会場でのエアーボリュームまでと国内でもっともTRIO+6BASSHORNを鳴らしてきた私としては、正にそのフィナーレにふさわしい体験であり、 これまでに述べてきた理論の認証体験でもあった。 私は…、数あるスピーカーは往々にして二つの種類に分類できると考えている。 一つはスピーカーの音質調整をユーザーに任せるという考え方、言い換えればユーザーのルームアコースティックに合わせて自由度のあるセッティングが出来るように配慮されたスピーカーたちだ。 例を挙げればJBLの4343シリーズのようにウーファー以外のユニットにすべてアッテネーターが付いているもの。 インフィニティーやジェネシスのように、アーノルド・ヌデール氏が設計したスピーカーはサーボアンプで低域を自由に設定し、中・高域もアッテネーターによって自由にレベル設定が出来てしまう。 もう一つは設計者の感性をそのままに使用するという調整箇所がまったくないスピーカー。 AVALON、WILSON、B&W、lumen white、などが代表的なところだろう。 私は両者ともに、その設計思想を認めるものであり、それはそれでいいのだが、このAvantgardeだけは上記のようにポンとおいて"それなりの音"が出るというスピーカーではないということを 本当に強く印象に残すことになったのである。 その第一の要因は、上記の二種類のスピーカーのなかでも前者の場合には電気的にいじれる調整手段をユーザーに開放したということなのだが、それらは"ほぼ量的な問題"ということで、 初心者であっても聴きながら経験を積んでいくうちにひとしおのレベルまで持っていけると思う。 しかし、Avantgardeの調整方法というのはサブ・ウーファーの調整も前述のように重要ではあるのだが、位置的、角度的なアライメントの調整が ことのほか"楽音の質的な問題"として重要になってくるということなのだ。 第二の要因として上記の調整箇所がまったくないAVALONなどを事例に挙げて考えられるのだが、まったくいじれないということに関してはよしとしても 室内でのセッティングは位置的にも大きな変化を見せるものである。言い換えれば間接音の影響をうまく処理していかないと一定レベルを超えられないということだろう。 しかし、Avantgardeは極論を言えば後方の壁にぴったりと密着させても、図2で表現されているように主要な楽音には影響がないのである。これはセッティング上でのメリットとして上げられるものだが、 逆に考えればAvantgardeの製品はそれ自身の質感の調整をうまくやらなければ本領を発揮しないということだと思う。これは前記同様に位置的、角度的なアライメントの調整と言うことになる。 そこで前述の大きく分けてスピーカーにおける二つの分類に対して、Avantgardeの登場によって第三の分類が発生したと私は考えているのである。 それは、前記の二つの分類はAvantgardeの論法を借用すれば間接音と直接音をほぼ半分ずつリスナーに届ける形式というスピーカーの分類と、Avantgardeのように直接音を85%も聴かせるという違いである。 これによって、Avantgardeの場合には、それ自身の調整が音質に顕著に現れ、単に置いただけでは本領発揮はしないどころか、オーナーが望まない音質にまで落ち込んでしまう可能性もあるということだ。 直接音の割合が多いだけに、それ自身の使いこなしが問われるということだろう。 難しい表現になってしまったが、これを簡単に言えば自分はこういう音が好きなんだ…という美意識をきちんと持たれていることがユーザーに求められると言うことだと思う。 私も本当に数多くのスピーカーを扱ってきたが、Avantgardeは本当にスィートスポットが極小である。 ジャストミートすれば素晴らしいが、外してしまうと期待はずれになりやすい。 それだけオーナーの資質を問うスピーカーなのだが、それに挑戦して見合うだけの価値が十分にある。 どれだけ多くのスピーカーを買い換えてきたかが問題ではない。むしろ、ひとつのスピーカーに対してどれだけ情熱を傾けてチューニングしてきたか、 その愛着心と執念とも言うべき真剣な取り組みを信条とされるユーザーにこそAvantgardeをお勧めしたい。 前章でも述べているが、Holgar Fromme氏は理論の上で理想とされるspherical hornを自分自身でソフトウェアから開発して具現化した言わばパイオニアである。 高性能なユニットをカタログ上で選び、または特注して他社からキーパーツの供給を受けてスピーカーを作っているメーカーと根本的に違うところはここである。 理論を実証し製品のすべてを自社で製作する。そのモノ作りの根底からの自信がなければ、到底"Avantgarde"などいう社名を思いつかないだろうし名前負けしてしまうことだろう。 そして、オリジナリティーということでViolaの熟成した技術力と感性は、彼らの伝統的な技法を踏襲しながらもアンプ分野における"Avantgarde"を成し遂げてきたものだと考えている。 これらの作品が輸入されたことに私は大きな喜びを感じるものである。そして、日本のオーディオシーンにおいても"Avantgarde"な感性が広まっていくことを期待して止まない。 |
最終項へ

