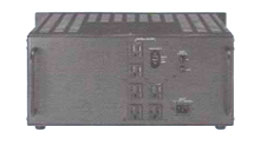|
12月4日、5日に行った電源アクセサリーメーカー合同マラソン試聴会ですが、多くのお客様にご来店いただき、おかげさまで無事に終了することができました。 ご参加いただいたお客様へはこの場をお借りして、深く御礼を申し上げます。 さてこのイベントですが、事前にご連絡しておりませんでしたが、ご参加頂いたお客様へアンケートを実施させていただきました。 そのアンケートですが
これはメーカーサイドからの要望もありましたが、ご参加いただけなかったお客様へ今後の電源選びの参考にもなるのではないかと思い実施させていただいた次第です。 ご協力いただいたお客様へは改めて御礼を申し上げます。 それでは、前置きはここまでにさせていただき、それぞれの部門ごとのランキングを発表させていただきます。 ノミネートいたしました機器は、以下の通りです。 |
|
それでは、各部門毎の結果とREPORTです。
ここでは、CSEの人気が高かったようです。 ランクインした3機種の共通点として通常のパワーアンプまで電源供給できるだけの容量があり、 パワーアンプに使用した時の印象が、評価のポイントになったのではないでしょうか。 今回のCSE FX-1500、PS AUDIO P1000に関しましては共通の機能を持っておりまして、その機能というのは、周波数の切り替えです。 FX-1500の場合50/60/80/100/電源同期の切り替え、P1000の場合「SINE」モードにおいて出力周波数を50Hzから120Hzまで1Hz刻みで可変する事が出来ます。 ご存知かと思いますが、日本では西日本が100V/60Hz、東日本が100V/50Hzとなっていて、通常西日本の方が電源事情が良いと言われるのは、この周波数の違いによるものです。 今回のデモではFX-1500とP1000の2機種は周波数を上げて使用しましたので、解像度/情報量の評価が高かったのかも知れません。 しかし、単に周波数が高ければ良いという事ではありません。 周波数を上げれば解像度は上がりますが、力感は減りますのでご注意ください。 |
|
解像度/情報量 部門とは違う結果が出ました。 4F “H.A.L III”では、それぞれのコンセントへ独立したブレーカーより個別に電源供給しておりますが、 そのコンセントの電圧はテスターでの測定では通常104V程度になっております。 H.A.L3ではパワーアンプを使用する場合、力感だけとってみると、壁やタップから直接とったほうが良い場合の方が多いように感じます。それは元々104Vある電圧を 100Vに落とす訳ですから当然とも言えます。逆に100V来ていないご家庭の場合での評価はかなり変わって来ることになります。 これはそれぞれの電源事情で変わってきますので判断に困りますが、一度テスターでご家庭のコンセントの供給電圧を測ってみてはいかがでしょうか。 さてランキングですが、アシスタンスデザインの『VERSA220Q』の評価が高かったようです。 このVERSA220Qですが、一つの筐体の中に4つのトランスを持っております。 出力端子は、一つのトランスから2口コンセントが一つ(合計8出力)のみとなっておりますが、これはそれぞれの機器をアイソレートできるという大きなメリットがあり、 それがこの機器の魅力の一つです。 また、力感を減らすことなくクオリティを上げることが出来るのもこの4つのトランスに秘密があると思います。 信濃電気の『HSR-1000R』は、そもそもがスタジオユースということもありまして、力感は非常に高いです。 |
価格もさることながら、音楽的・オーディオ的な面白さを感じるところが大きかったのでしょう。 ここでランキングされていない、CSEと信濃電気ですが、ある意味中庸で色付けが少ないとも判断されます。 信濃電気の場合はスタジオでの評価が高いのですが、良い意味でも悪い意味でも色付けが少ないからかもしれません。 PS AUDIOに関しましては中域に独特な癖がありますが、これが良いと判断したお客様も多かったようです。 しかし、音楽性の違いも顕著に出てきたということは、電源も重要なオーディオ機器だという証明になったのではないでしょうか。 ここでちょっと補足をさせていただきたいことがあるのですが、今回のイベントでは取り上げませんでした各電源機材へ供給する電源ケーブルの違いについてです。 アシスタンスデザインやCSEの上級機種の場合パワコンを用いておりますので変更できませんが、その他の機種の場合変更が可能となっております。 それぞれのメーカーで電源ケーブルを変更したところ、まったく違う音色を出してくれました。 電源を作り直してはいるものの、そこまで入ってくる電源でかなり違うことが解りました。 もし、今電源機材をご使用のお客様で、付属の電源ケーブルをお使いでしたら変更してみてはいかがでしょうか。 |
AIT-160TWの魅力は一つの筐体に、トランスを2個搭載していることがあげられます。 そのトランス各々に対して2口コンセントが一つずつ(=合計4出力)付いておりますので、 片方のトランス側にデジタル機器、もう一方のトランス側にアナログ機器を接続し、デジタルとアナログのアイソレーションを図ることで一層質の高い音を狙うことができます。 また内部のジャンパーにより120V出力も可能になっております。 そういった機能を持ち、12万円という価格設定がコストパフォーマンス部門でトップとなった大きな要因の一つだと思います。 CSEに関しては、MK2になりデザインも一新され、よりクォリティの高いものになっております。 出力周波数が60Hzですので、東日本にお住まいのお客様には著しい効果が期待できます。 PS AUDIOは、最近価格が下がったということもあり、\280,000という定価でありながらもコストパフォーマンスが高いとの評価を受けたのでしょう。 個人的な印象としましても、ここまでの機能を持ち自由に遊べるPS AUDIOに関しては面白い存在だと思います。 但し、P500はあまり負荷をかけすぎると、空冷用のファンが回りだしてしまいますので神経質なお客様には不向きかもしれません。 |
|
機能性の部門でもトップはアシスタンスデザインでした。 その機能性はコストパフォーマンスで説明しておりますので、省かせていただきます。 機能性と一言で申し上げるのはかなり難しいことですが、電源に何を求めるかだと思います。 例えば周波数の切り替え、電圧の変更等ございますが、PS AUDIOに関しましてはそれ以外にも多くの機能が用意されております。 まず、P500、P1000ですが独自のマルチウェーブIIによって再生音を調整することもできます。 また突然の電源トラブルに対応できるように3重のプロテクション回路が内蔵されております。 PD4.7やPD3.5は、3重のプロテクション機能の他に、裏側のスィッチ切り替えにより出力をゾーンごとに、 常時出力、フロント電源スィッチに連動、ディレイ出力の3パターンの切り替えも可能となっております。ホームシアターでの機能性は抜群なのではないでしょうか。 なお、ランクインを逃してしまったCSEですが、FX1500は周波数の切り替え、TX2000はゼロクロススィッチ,アース切り替えなどの機能がついております。 ゼロクロススィッチはCSEの機器に対する思いやりからできた機能ではないでしょうか。これも大きく評価できるポイントだと思います。
|
これは機能性、サイズ、価格の3要素トータルでの評価が高かった結果だと思います。 意外に検討したのが信濃電気でした。意外と言ってはメーカーに失礼ですが、モニター思考のお客様からの評価が高かったようです。 信濃電気の場合、多くの音楽スタジオやちょっと違うところでは大型アミューズメントパークで使われているようです。逆に言うと他のメーカーの電源はスタジオではほとんど目にしないと思います。それは、信濃電気の信頼性や耐久性、色付けの少ない音色が、エンジニアのニーズにあっていると言えます。 各項目では上位ではありませんが、平均点が高く2位にランクインされました。 |
|
今回のイベントでは、改めて電源の面白さが浮き彫りになりました。 電源といっても、今回のようなトランスやレギュレーター以外にも電源ケーブルや電源タップ、更に突っ込んで言えば配電盤やコンセントまでのケーブル。 それ以外にも大元から見直し、200Vを引き込み、機器を200Vに変更したり、200Vから100Vにステップダウンして使用しているお客様もいらっしゃいます。 このことでも、電源が機器に及ぼす影響が大きいということがお解かり頂けると思います。 PSE(電気用品安全法)による制約で、それまでの多くの電源ケーブルや電源タップが販売中止になり電源への興味が薄れていると思いますが、 改めて今回使用した電源トランスなどに目を向けてみてはいかがでしょうか。 今回のイベントは、持ち時間40分という制約がありましたので、メーカーによっては説明が長びき、聞いて頂く時間が少なくなったり、出番の無い機器も出てきました。 選曲に関しても、各メーカーが持ち込んだCDを使用しましたので、本当の聞き較べにならなかったかも知れません。 これは私のプランニング不足であったと反省しております。 ただ、各メーカーの製品に対するこだわり、音色の違いはご理解いただけたのではないかと思っております。 集計結果はあくまでもご参加いただいたお客様だけによりますランキングですので、これが全てではございません。 これをご覧になり、電源に興味を持たれたお客様は可能な限りご試聴の上、納得してお買い求めいただければ幸いです。 また、電源でお困りのことがございましたら、私を含め、各メーカーでバックアップさせていただきますのでご相談くださいますよう申し上げます。
|
NEWSのページに戻る